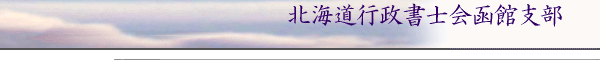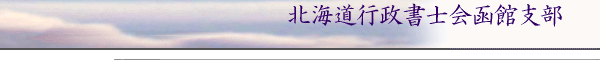
『今も現役の和文タイプライター』
初代 東畑道之助(巴屋)
(佐藤 聰)
私の事務所の機器コーナーには、パソコンとカラーコピー機の間に、今では珍しい和文
タイプライターがある。開業して27年間、今も立派に現役で働いてくれている。私にとっては、古き良き友みたいなものである。


昭和59年の1月に晴れて合格証を手にした私は、妻と相談して5月31日の結婚記念日に開業することを決め、早速開業準備に取り掛かった。
先ず、事務所をどこにするかである。ラッキーなことに自宅の隣が妻の実家の貸家であったが、タイミングよく引っ越ししたので、事務所に改装するための工事が急ピッチで進められた。一方、事務所に備える机や事務用品、参考図書、コピー機、FAXなど、取りあえずは必要最低限のものを手配した。金もかなりかかったが、先行投資である。
さて、その当時パソコンとか文章作成のワープロ機が出ていたとは思うが、そんなことには目も向けず。なぜか、和文タイプに惹かれていったのである。確かにその当時、司法書士事務所の多くは、和文タイプで申請書を作成していた時代であり、街には和文タイプの店があって外からもタイプの打ち込む音が聞こえてきたものである。
私は、字を書くのが好きである。ペンでも筆でも。我が青春時代には、ラブレターもよく書いたもので、特に妻宛のラブレターは私の手元に戻って、今では桐の箱に収められて金庫の中にある。
受験勉強の時も、法律図書は読むことよりも、書いて覚えたような気がする。各科目のポイントを大学ノート数冊に書きためて頭にたたきこんだ。だから開業しても書くことは苦にならないとは思っていたが、それでも正式な書類作成には和文タイプライターは、必需品でしかも自分で打ち込めるようにならなければならないと真剣に思った。
どこか教える所がないものかと電話帳を見たら、和文タイプ学校なるものがあった。どんなところでどんなことをするのか全く判らないまま、とにかく学校を訪ねて入学可能かどうか聞いてみた。出てきた教師らしい人が私をジロジロ見ながら"あなたが習いたいんですか?"と怪訝そうな顔をしている。私は"男じゃだめなんだ"と思ったが、どうもそうではないらしい。ぶっきらぼうに、その教師らしい人が"夜のコースでよかったら来週から来てください"と言うわけで、三ヶ月間そのタイプ学校に通うことになった。
とにかく生まれて初めて触るもので、できるかどうかかなり不安であったが思い切り飛び込んでみた。
学校に行ってみると、タイプ機が10台ほど置かれた教室に通されたのであるが、案の定、生徒はみな若い女性ばかりであった。いわゆる、タイプ嬢になるための訓練生である。
私が教室に入るや否や視線が一斉に私に集まった。"なに!このおじさん!!"一瞬"
場違いのところに来てしまったか!"と恐怖にも似た違和感を覚えたものである。しかし、
そんなことも言ってられないので、40歳のおじさんは、若いOLに混じってタイプのいろはに挑戦した。
一通りタイプ機の取り扱いを習った後、原稿用紙を渡されて、"とにかく打ってみなさい"と言う。打とうとすると活字が文字盤のどこにあるのか探すのにかなりの時間を要した。ようやく活字を見つけても、今度はカーソルをあわせてその活字を拾い上げ打ち込まなければならない。これには、コツがあってなかなか難しいのである。慣れないことだけに肩は張るは、目はしょぼつくし、結局初日は、一行打ち込むのに一時間もかかるなど散々な一日であった。
でも、一ヶ月も経つと活字の配列にも、カーソルを合わせるのも慣れ始め、一定の時間で文章も間違いなく打てるようにはなった。後は、練習あるのみと思って、だから学校は途中で行かなくなった。悪い生徒である。
狭いながらも事務所も完成し、什器備品の搬入となった。タイプライターも高額な物であったが何とか購入した。そして、毎日のように練習に励んだのである。
さて、この友は日本タイプライター㈱製で、名前をユニライターと称し、何と自動打ち込み式である。だから、手動式と違って一定の強さで打ち込むので出来上がりがきれいなのである。右手でカーソルを動かしも文字盤(2,520字)の活字に合わせて、左手でキーをワンタッチ押すだけである。使うほどに慣れ、すっかり私の大切な頼りになる存在となった。
開業当時、例えば農地法の各種許可申請などは、北海道行政書士会の指定用紙を使用していたので、毎日のようにカーボン紙を挟んでタイプで打ち込んで作成したものである。
これまで何百件の書類を作ったことか……。
やがてパソコンが登場してワープロ機能も充実し、タイプもその主役を明け渡すことになったのであるが、今でも既定用紙などには好んでタイプで打ち込み、会話をしながら使いこなしている。所々錆びていたり、用紙受けローラーが剥がれ落ちたりと、私と同じようにご老体でガタが来始めてはいるが、それなりの歴史と雰囲気を漂わせ、今も存在感たっぷりである。
私と共に生涯現役を目指し、私のことを思い支えてくれる古き良き友なのである。 (完)